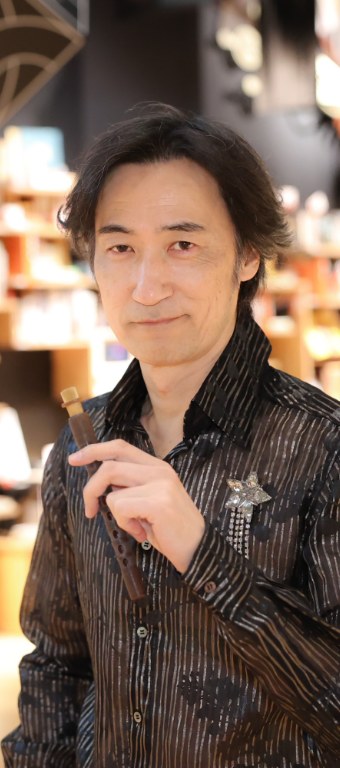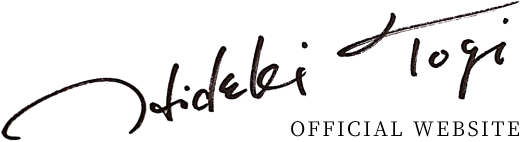
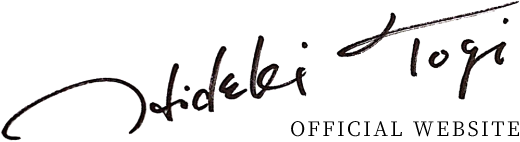
「笙」「篳篥」「龍笛」についてnew !
雅楽の中心的な役割である管楽器、その代表的なものが「笙」「篳篥」「龍笛」です。1500年前、あるいは2000年以上前にアジア大陸のどこかで発祥し、古代中国や朝鮮などの国々で発展し、飛鳥時代に日本に渡って来てからほとんどその形を変えることなく生き続けているのです。その音色も千年以上の時を経てもほとんど変化せずそのまま伝わっているのです。
「笙(しょう)」は17本の竹を束ねたような形をして、その内の15本の竹の根元に金属のリードが付いており、息を吹いたり吸ったりすることでそのリードが振動して音となります。和音を奏するのが主で、他の楽器の音を包み込むような役割があります。その形は鳳凰が翼を立てている姿とされ、古代からその音色は「天から差し込む光」を表すとされています。またこの「笙」が西洋のパイプオルガンやアコーディオンのルーツであるともいわれています。
「篳篥(ひちりき)」は18センチほどの竹の筒に蘆を削って作ったリードを差し込み、そのリードから息を吹き入れて音を出す縦笛です。竹には九つの指穴があいており、細いヒモ状にした桜の木の皮を巻き付け、漆で仕上げてあります。主に主旋律を担当する楽器で、なだらかな抑揚をつけながら音程を変えたりするのが特徴で、この奏法を塩梅(えんばい)といいます。音域は狭く、男性が普通に出せる声の範囲とほぼ同じ1オクターブと1?2音です。古代からこの楽器の音色は「人の声」つまり「地上の音」を表すとされています。西洋楽器のオーボエなどのルーツともいわれています。
「龍笛(りゅうてき)」は篳篥の旋律にまとわりつく副旋律を担当することが多く、ときには主旋律も担当したりします。7つの指穴がある横笛で、2オクターブの音域を持っています。「龍笛」という名前の通り、天と地の間を行き交う「龍の鳴き声」を表しているとされています。つまり天と地の間の空間を象徴しているのです。
雅楽ではこれら「笙」「篳篥」「龍笛」を合奏することが基本の表現となります。それは「天」「地」「空」を合わせる、つまり音楽表現がそのまま宇宙を創ることと考えられているのです。 またこれらの楽器の音は耳や頭で聴くというよりは、空気のように肌から自然に入ってきて心のどこかに触れて感じたり、あるいは意識外のところで細胞が勝手に反応したりするのではないかと思います。 人間もひとつの宇宙ですから・・・・。